コーヒーのカフェインは、風邪の倦怠感や頭痛の緩和に対し、間接的な効果が期待できます
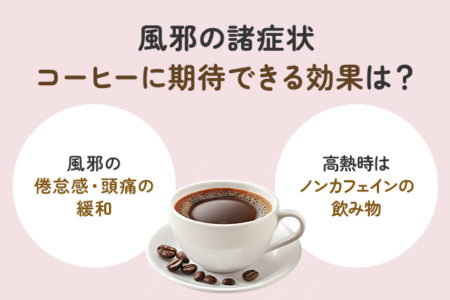
コーヒーに含まれるカフェインは、風邪の症状に対してどのような効果があるのでしょうか?本記事は、カフェインの効果・効能や副作用、そして注意点について解説します。
目次
カフェインとは?
カフェインとは、自然由来の有機化合物にあたるアルカロイドの一種で、コーヒー豆・茶葉・カカオ豆などに含まれています。キサンチン誘導体に分類されるカフェインは、例えば気管支喘息などの治療薬にも活用されています。
カフェインには苦みがあるため食品添加物に登録されているほか、中枢神経を刺激して覚醒作用をもたらすことから、エナジードリンクなどにも使われる成分です。「眠気覚ましにコーヒーを飲む」など、カフェインの摂取は目が覚める、気分がすっきりするなどのイメージがあります。
カフェインの効果・効能
 コーヒーの成分のひとつであるカフェインは、あらゆる効果・効能があるといわれています。清涼飲料や栄養ドリンク、市販の鎮痛剤などに使われるカフェインに期待される効果と効能を、6つ説明します。
コーヒーの成分のひとつであるカフェインは、あらゆる効果・効能があるといわれています。清涼飲料や栄養ドリンク、市販の鎮痛剤などに使われるカフェインに期待される効果と効能を、6つ説明します。
覚醒作用
カフェインは中枢神経を刺激して、覚醒させる作用が期待されています。人が疲労を感じたときに眠くなる原因は、体内でアデノシンが生成され、アデノシン受容体と結びつくと心拍数が低下して体がリラックスするためです。
カフェインはアデノシンに似た構造をしており、先に受容体と結びつくため、心拍数が下がって眠くなることを防ぎます。同時にドーパミンなどの分泌を促進し、注意力や集中力が高まり、仕事や勉強などでのパフォーマンスアップを期待できるのです。
鎮痛作用
カフェインは血管収縮作用があるといわれており、脳血管が拡張して起きる片頭痛の緩和を期待できます。市販の鎮痛剤にはカフェインを使ったものがあり、無水カフェインの錠剤は片頭痛の治療薬として処方されています。
また、片頭痛だけでなく筋肉痛をやわらげる働きも期待できるので、風邪などの症状の緩和にも役立つ成分です。
気分の改善
カフェインをとると、ドーパミンやセロトニンの分泌を促し、気分がすっきりする・高揚するなどの効果を期待できます。ドーパミンとは神経伝達物質のひとつで、快さを感じる脳内の働きに関わっています。
セロトニンはストレスに働く神経伝達物質で、安心感や心の安定に関わっており、精神安定剤に似た構造です。セロトニンが不足すると、慢性疲労・ストレス・やる気の低下・協調性低下などがおき、うつ症状が見られるケースもあります。
軽度のうつ症状であれば、カフェインを摂取することで改善に寄与する可能性があります。
運動パフォーマンスの向上
適度にカフェインを摂取して有酸素運動や無酸素運動を行うと、スピードや持久力のアップにつながるというデータを、国際スポーツ栄養学会が発表しています。筋トレをするときにカフェインをとると、覚醒随意最大収縮や筋持久力が高まるので、効率よく筋トレを行えます。
しかし、カフェインをとればとるほど向上するわけではありません。個々でカフェインによる効果の感じ方が異なり、自分にとってはちょうど良くても、他人には強すぎると感じる場合があります。
カフェインのとり過ぎは健康へ悪影響を及ぼす恐れがあるので、体質に合った適量のカフェインをとりましょう。
代謝の促進
カフェインには基礎代謝を上げる働きがあるといわれ、筋トレやダイエットに嬉しい作用を期待されています。有酸素運動の30分前にカフェインをとると、脂肪燃焼スピードが上がるという研究結果があるため、ダイエットにも効果的です。
このとき飲むコーヒーは、体重1kgあたり3mgのカフェインを含む、濃いものにしましょう。
利尿作用
腎臓の血流を促進して尿量を増やし、体内の水分を排出しやすくする働きも、カフェインに期待されています。利尿作用は、体内の余分な水分を外へ出してためにくくするため、むくみ予防にも役立ちます。
風邪に対するカフェインの効果
 覚醒作用や鎮痛作用があるといわれるカフェインですが、直接風邪を治療するなどといった科学的な根拠はありません。しかし風邪の諸症状を緩和する、以下の3つの間接的な効果を期待されています。
覚醒作用や鎮痛作用があるといわれるカフェインですが、直接風邪を治療するなどといった科学的な根拠はありません。しかし風邪の諸症状を緩和する、以下の3つの間接的な効果を期待されています。
倦怠感の軽減
風邪を引いたときに感じやすい、だるさや眠気の抑制にカフェインが役立ちます。市販の風邪薬にはカフェインを含むものがありますが、カフェインの含有量はコーヒー1杯分を下回ります。
風邪の症状によっては、コーヒーを1杯飲むと体調の改善に役立つでしょう。
頭痛の緩和
風邪が原因で起きている頭痛や関節・筋肉の痛みは、カフェインをとると緩和される可能性があります。ただし、脳の血管が何らかの原因で急に拡張して引き起こされる、片頭痛の場合に期待できる効果です。
長い時間同じ姿勢を続けた、または精神的なストレスがかかり続けたことなどによって起きる緊張型頭痛は、カフェインをとると逆効果なので注意しましょう。緊張により収縮した血管がいっそう収縮し、頭痛の悪化を招く恐れがあります。
気管支拡張作用
カフェインは一時的に気管支を拡張して咳を鎮め、呼吸を楽にする働きがあるといわれています。抗炎症作用も期待できるので、鼻づまりの症状を軽くする可能性もあります。
ただし、喘息があり治療を続けている場合はカフェインのとり過ぎによって、頭痛や動悸を引き起こすかもしれません。なぜなら、テオフィリン系の喘息治療薬を飲んでいると、成分がカフェインと似ており、薬が効きすぎてしまう恐れがあるからです。
カフェインの副作用
健康に役立つ多くの働きを期待されるカフェインですが、副作用もあります。コーヒーを飲み過ぎるなど、毎日必要以上にカフェインをとった場合の副作用を3つ説明します。
不眠
カフェインをとり過ぎると、なかなか寝付けない・夜中に何度もトイレに行く・眠りが浅いなどの状態から、不眠になる可能性があります。これは、カフェインの覚醒作用が眠りを妨げるためで、カフェインをとるタイミングを誤ると、眠れない日々が続くかもしれません。
カフェインをとるとすぐに吸収され半減期は3.5~5時間ですが、特に夜の摂取は控えましょう。寝る時間を考えてコーヒーなどを飲む時間を決め、眠りを妨げないとり方をします。
心拍数の増加
カフェインには強心作用が期待されるため、心拍数が増加するケースがあります。血圧が上昇し心臓に負担がかかると1分あたりの心拍数が100回を超え、動悸を覚える恐れがあります。
悪化すると、心拍数は1分あたり140回を超えて血圧が下がりショック状態になる、または心室細動や心室頻拍などの不整脈が起き、最悪の場合心停止に至るかもしれません。心疾患のある人は、カフェインのとり方に注意が必要です。
依存性
眠気や片頭痛を抑えるなどの目的でカフェインの摂取量が増えていき、長期間にわたって過剰摂取を続けた場合、カフェイン依存を引き起こす恐れがあります。カフェインを摂取していない状態で、倦怠感・眠気・集中力の低下・頭痛・不安・抑うつ・胃の不快感や吐き気などの症状があると、症状を緩和するためにさらにカフェインをとり依存が悪化するケースがあるので、適量を守ることが大切です。
風邪のときにコーヒーを飲む注意点
 風邪を引くと起こりがちな症状は、コーヒーを飲んでカフェインをとると緩和する可能性があります。しかしカフェインには副作用があるため、3つの注意点を守って飲みましょう。
風邪を引くと起こりがちな症状は、コーヒーを飲んでカフェインをとると緩和する可能性があります。しかしカフェインには副作用があるため、3つの注意点を守って飲みましょう。
適量の摂取
健康面の異常がない成人が、1日に摂取しても安全といわれるカフェインの摂取量は400mgです。コーヒーに換算すると約4~5杯ほどですが、コーヒー以外にお茶類やチョコレートなどにも含まれているため、コーヒーだけを基準に考えず適量の摂取を心がけましょう。
エナジードリンクや眠気覚ましをうたう清涼飲料は、コーヒー2杯分のカフェインを含む場合があります。カフェインの含有量表示が100mlあたりになっており、一見少ないと感じるケースもあるので、1本あたりに換算してカフェイン量をチェックしてください。
個人差がある
カフェインをとったときの感じ方には、個人差があります。カフェインに敏感な人は、一般には1日400mgまで安全といわれるカフェイン摂取量からさらに抑えた方が安心です。
またこの数値は成人に対するものなので、子供もカフェインの摂取量をより抑えましょう。妊娠中・授乳中の人はあまりカフェインをとらないことを推奨されていますが、日本で具体的なきまりはありません。
例えばWHOは1日あたり300mgまで、欧州食品安全機関は1日あたり200mgまでとしています。この数値を参考に、200~300mgにとどめることをおすすめします。
他の薬との相互作用
カフェインは、他の薬の効き目に影響を及ぼす恐れがあります。風邪のときに市販の風邪薬や鎮痛剤などを飲み、さらにコーヒーを飲むと相互作用が起きる可能性があるため、飲み方には注意が必要です。
風邪の症状によってはコーヒーを飲むのを控えた方が良い
 健康状態や症状によっては、コーヒーに含まれるカフェインの作用により、悪化する恐れがあります。次の3つにあてはまる場合は、コーヒーを控えましょう。
健康状態や症状によっては、コーヒーに含まれるカフェインの作用により、悪化する恐れがあります。次の3つにあてはまる場合は、コーヒーを控えましょう。
熱が高いとき
高熱が出ると体内の水分が失われやすく、利尿作用の期待されるコーヒーを飲むと、必要な水分が排出され脱水症状になる恐れがあります。熱が高いときはコーヒーを控え、お水・スポーツドリンク・経口補水液・麦茶などカフェインを含まない飲み物を選びましょう。
同時に鼻づまりがあり鼻の通りをよくしたいときは、爽やかですっきりとしたペパーミントティーがおすすめです。
睡眠不足のとき
風邪で症状が辛く睡眠不足になったときは、コーヒー以外の飲み物で水分補給をします。回復には十分な睡眠が必要ですが、カフェインには覚醒作用があるといわれています。
症状の改善目的でコーヒーを飲むと睡眠の質を低下させるので、コーヒーは控えてください。代わりに、症状の緩和に役立つビタミンCを豊富に含む、温かいレモン水がおすすめです。
胃腸が弱っているとき
風邪で胃炎や下痢が起きている場合、コーヒーを飲むと胃腸に刺激を与える恐れがあります。なぜなら、カフェインに期待される胃酸分泌作用が症状を悪化させる可能性があるからです。
リラックスしたいときには、飲むと心が落ち着くといわれるカモミールティーをおすすめします。
(まとめ)コーヒーのカフェインは風邪に効く?効果や副作用などを解説
コーヒーのカフェインは、風邪の倦怠感や頭痛の緩和に対し、間接的な効果が期待できます
カフェインは覚醒作用や代謝促進など健康に嬉しい働きが、数多く期待されています。しかし風邪の治療に直接効果があるわけではないため、必要な栄養素や水分、休養をとって回復につとめましょう。
風邪の症状が悪化すると眠りにくくなる場合があり、カフェイン含有の鎮痛剤などを適度に使うと、倦怠感や頭痛の
緩和に役立ちます。カフェインは適量を守り、個人の体質や健康状態応じて摂取しましょう。



