1歳児で花粉症と診断されることはまれですが、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなど似た症状が出ることはあります
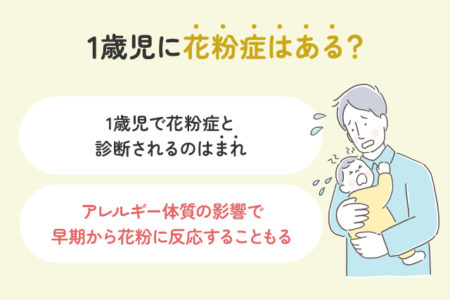
花粉症は大人だけの病気だと思われがちですが、実は子どもにも発症する可能性があります。特に季節ごとに鼻水やくしゃみが続くと「花粉症ではないか」と心配になる保護者も多いでしょう。
さらに1歳児は症状を言葉で表現できず、風邪や他の病気と区別がつきにくいのが特徴です。この記事では、1歳児に見られる花粉症の可能性のある症状や受診の目安、家庭でできる予防策や成長に伴う注意点を詳しく解説します。
目次
1歳児でも花粉症になる?
 子どもの花粉症は大人とは少し異なります。そもそも何歳頃から発症するのか、その目安を知っておきましょう。
子どもの花粉症は大人とは少し異なります。そもそも何歳頃から発症するのか、その目安を知っておきましょう。
何歳から発症するの?
花粉症は花粉に繰り返し接触することでアレルギー反応が起こる病気です。医学的には一定の曝露歴が必要とされ、発症は3歳以上で多くみられます。特にスギ花粉では、2〜3シーズン続けて接触した後に症状が現れるのが一般的です。
ただし、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーを持つ子どもは、アレルギー体質の影響で早期から花粉に反応することもあります。家族にアレルギー疾患がある場合も注意が必要です。
こんなサインに注意!花粉症が疑われる場面
1歳児で「花粉症かも」と感じるのは、特定の季節に鼻水やくしゃみが繰り返し出るときです。日本では春のスギ花粉、初夏のヒノキ、秋のブタクサやヨモギなど、年間を通じて様々な花粉が飛散しています。
例えば春先になると鼻水が長引く、秋になると夜間に鼻づまりが悪化する、といったパターンがあれば「季節性」を示す可能性があります。
ただし1歳児は免疫が未発達で風邪をひきやすいため、症状だけで判断せず慎重に経過をみることが大切です。
風邪と花粉症を見分けるポイント
1歳児の花粉症を判断するには、風邪や感染症との違いを理解する必要があります。
風邪は発熱や咳を伴うことが多く、数日から1週間程度で回復するのが一般的です。一方で花粉症は基本的に発熱を伴いませんが、大人と同様に1歳児でも微熱を示すことがあります。
鼻水の質にも違いがあり、花粉症は透明でさらさらとした水様性の鼻水が特徴です。風邪では黄色や緑色の粘性が強い鼻水が続くこともあります。また、花粉症は「毎年同じ時期に症状が出る」点が大きな判断材料となります。
風邪と花粉症を見分けるチェックリスト
| チェック項目 | 花粉症の可能性が高いのは? | 風邪の可能性が高いのは? |
| 症状が出た時期 | 毎年、決まった季節(春や秋など) | 季節に関係なく、突然 |
| 熱があるか? | 基本的にはありません。あっても微熱程度 | 高熱が出ることが多い |
| 鼻水の様子 | 透明で、水のようにサラサラしている | 黄色や緑色で、継続気がある |
| 目の様子 | 頻繁に目をこす、涙が出る、赤く充血する | あまり変化がない |
| 症状の長さ | 数週間から数ヶ月と、当面続く | 数日から1週間程度で治まる |
1歳児に見られる主な花粉症の症状
 1歳児は自分のつらさを言葉で伝えることができないため、保護者が行動や体調の変化に気付くことが重要です。ここでは代表的な症状を3つに分けて紹介します。
1歳児は自分のつらさを言葉で伝えることができないため、保護者が行動や体調の変化に気付くことが重要です。ここでは代表的な症状を3つに分けて紹介します。
止まらない鼻水や鼻づまり
透明で水のような鼻水が止まらず、ティッシュで拭いてもすぐに出てきてしまうのは典型的なサインです。
鼻づまりが強いと母乳やミルクが飲みにくくなり、授乳や食事に支障をきたします。長期間続くと食欲不振や体重増加の停滞にもつながり、成長に影響を及ぼす可能性があります。
目をこする、まぶたが赤くなる
花粉症では目のかゆみや赤みが目立ちます。1歳児は「かゆい」と言えないため、頻繁に目をこすったり、涙が多くなったり、まぶたが赤く腫れたりする行動から判断します。
強くこすり続けると角膜を傷つける恐れもあり、結膜炎を併発することもあるため注意が必要です。アトピー性皮膚炎を持つ子どもは特に症状が強く出やすい傾向があります。
夜泣きや寝つきの悪さ
鼻づまりは夜間に悪化しやすく、眠りを妨げます。そのため夜泣きが増えたり、寝つきが悪くなったりするケースもあります。保護者も何度も起こされるため、家庭全体の生活リズムに影響を及ぼします。
さらに、鼻づまりから口呼吸が習慣化すると、将来的に歯並びや顎の発達に関わるリスクもあると指摘されています。
医療機関を受診する目安と検査方法
 症状が続いたり、生活に支障が出たりする場合は医療機関を受診することが大切です。受診の目安や検査の流れを3つの視点から確認しましょう。
症状が続いたり、生活に支障が出たりする場合は医療機関を受診することが大切です。受診の目安や検査の流れを3つの視点から確認しましょう。
受診を考えるべきサイン
-
鼻水やくしゃみが2週間以上続く
-
微熱が長引く、高熱を繰り返す
-
夜間の鼻づまりで眠れない、食欲が落ちる
-
目の赤みやかゆみが強い
これらが見られる場合は小児科や耳鼻科を早めに受診すると安心です。
どんな検査をする?1歳児の検査方法
1歳児では血液検査によって花粉に対するIgE抗体を確認できます。ただし検査結果だけで診断が確定するわけではなく、症状の経過や季節性を含めて総合的に判断します。
皮膚検査は年齢的に難しいことが多いため、この時期は血液検査と問診が中心です。
アレルギー専門医に相談するメリット
小児科のみでは診断が難しい場合もあるため、アレルギー専門医に相談するのも有効です。花粉症だけでなく、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎、喘息なども総合的に診てもらえます。
家族にアレルギー体質がある場合や複数の症状が重なる場合には特に推奨されます。
家庭でできる花粉症対策
 日々の生活の中で、花粉を勝手に工夫することで、症状の軽減が期待できます。苦痛のつらさを少しでも考えてみましょう。
日々の生活の中で、花粉を勝手に工夫することで、症状の軽減が期待できます。苦痛のつらさを少しでも考えてみましょう。
外出時の予防対策
1歳児はマスクを正しく着けられないため、ベビーカーにカバーをつける、帽子をかぶせるなどの工夫が効果的です。
外出は花粉が多い午前10時〜午後2時を避けるとよいでしょう。外出前には花粉情報をチェックし、飛散量が多い日は外遊びを短時間にするのも有効です
帰宅後の工夫
帰宅したら衣服を玄関で脱ぎ、すぐに洗濯機へ。髪や肌に付着した花粉は入浴で洗い流すのが効果的です。難しい場合は顔や手足だけでもぬるま湯で洗浄するとよいでしょう。
鼻水で肌が荒れやすいため、保湿ケアも欠かせません。
部屋の中の花粉対策
室内では空気清浄機を稼働させ、床は掃除機と水拭きを併用して花粉を取り除きます。布団は布団乾燥機を活用し、洗濯物は部屋干しにすることで花粉付着を防げます。
こうした環境整備は、1歳児が快適に過ごせる空間づくりにつながります。
1歳児の花粉症はまれ?成長との関わり方

1歳児で花粉症と診断されるのは珍しいものの、似た症状や成長に伴う変化には注意が必要です。
花粉症が発症するメカニズム
花粉症は一度の接触で発症するものではなく、数年にわたり花粉にさらされ続けることで発症します。そのため1歳児で花粉症と診断されるのは非常にまれです。
ただし、家族歴やアレルギー体質がある場合には、将来的に発症するリスクが高まる可能性があるため注意が必要です。小さい頃から生活環境を整え、花粉を避ける習慣をつけることは、将来的な症状の軽減や予防につながります。
花粉症と間違えやすい他の病気
1歳児では、アデノイド肥大による鼻づまりやウイルス性鼻炎など、花粉症とよく似た症状を示す病気があります。特に花粉の季節にこれらの症状が悪化すると「花粉症かも」と誤解されやすいのが特徴です。
また、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎など、ほかのアレルギー疾患を持つ子どもは、鼻や目の症状が複雑に絡み合い、花粉症との違いをさらに見分けにくくする要因となります。
アレルギー体質は成長とともに変化する?
幼児期に花粉症に似た症状が見られても、成長に伴って症状が和らいでいく場合も少なくありません。1歳児の段階で症状があっても、その後どのように変化するかには個人差があります。
保護者が早い時期からアレルギーについて理解を深め、生活環境を整えてあげることが、将来的な健康維持や症状の軽減に大きく役立ちます。
(まとめ)1歳児に花粉症はある?症状と見分け方、予防・対策ガイド
1歳児で花粉症と診断されることはまれですが、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなど似た症状が出ることはあります
症状が長引く場合や生活に影響を及ぼす場合は花粉症以外の病気も含めて医師に相談することが安心につながります。家庭では花粉を避ける工夫を取り入れ、必要に応じてアレルギー専門医に相談しましょう。
正しい知識と予防策によって、1歳児の健やかな成長と家族の安心を守ることができます。
<出典>
- 環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」
- 厚生労働省「花粉症Q&A集」
- 厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「アレルギー性鼻炎」
- 久光製薬株式会社「子どものための花粉症対策」



