1歳児は食生活や生活リズムの変化から便秘になりやすいため、水分・食物繊維の摂取、規則正しい生活を心がけましょう
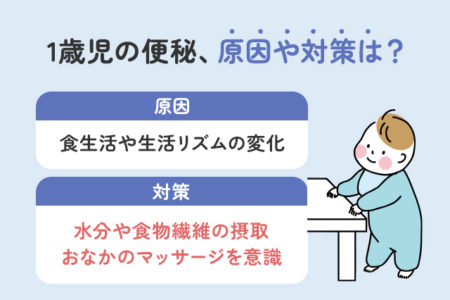
「2〜3日うんちが出ない」「硬くて泣いてしまう」――1歳前後は便秘に悩む子が少なくありません。成長や離乳食の進み具合、生活リズムの変化などが影響して便秘が起こりやすく、保護者が不安を抱えることも多い時期です。
多くは水分や食事、生活習慣の工夫で改善が期待できますが、症状が続く場合には医療機関の受診も必要です。本記事では便秘の原因と家庭でできる対策、受診の目安を整理しました。
目次
1歳児の便秘とは?判断の目安とサイン

まず、1歳児の便秘がどのような状態を指すのかを理解することが大切です。便の回数だけでなく、便の状態や排便時の様子を観察し、健康な排便との違いを知っておきましょう。
便秘の目安となる排便回数と便の状態
1歳児の排便回数には個人差が大きく、1日に数回出る子もいれば、2〜3日に1回の子もいます。大切なのは回数ではなく、「便の状態」と「排便時の様子」です。
コロコロと硬い便が続く、排便時に顔を真っ赤にして泣く、肛門が切れて血が付くといった場合は便秘と考えられます。逆に、2日に1回でもやわらかく無理なく出ているなら心配はいりません。
普段の排便の様子を観察し、お子さんの「いつものリズム」を知っておくことが大切です。
便の状態で見る便秘の目安
| 便の状態 | 特徴・観察ポイント | 健康状態の目安 |
|---|---|---|
| 柔らかくスルッと出る | 黄褐色〜茶色、においは強くない | 健康的で問題なし |
| 少しかため | コロコロせず、形はあるが無理なく出る | 個人差の範囲内 |
| コロコロと硬い | ウサギの糞のように小さい粒状 | 便秘のサイン、要注意 |
| 長くて硬い | 太くて乾燥し、排便時に泣く | 便秘が進んでいる可能性大 |
| 血が付着している | 肛門の切れや強い力みで出血 | 医療機関の受診を検討 |
健康的な排便との違いと悪循環
健康的な便は、やや柔らかく、スルッと短時間で出るのが特徴です。便秘になると、便が硬く乾燥して腸内に長く留まり、排便に時間がかかります。強い力みや泣き声、排便を嫌がる行動が見られる場合は要注意です。
硬い便による痛みの経験は「出すのが怖い」という気持ちにつながり、我慢が増えることで便秘が悪化する悪循環を生みます。食欲の低下やお腹の張り、機嫌の変化にもつながるため、小さなサインを見逃さないようにしましょう。
1歳児が便秘になる主な原因
 次に、便秘が起こりやすい背景を整理してみましょう。食事や水分、運動、心理的な要因など、1歳児特有の生活の変化が重なって便秘を引き起こすことがあります。
次に、便秘が起こりやすい背景を整理してみましょう。食事や水分、運動、心理的な要因など、1歳児特有の生活の変化が重なって便秘を引き起こすことがあります。
食生活(離乳食後期・完了期の影響)
1歳になると離乳食は完了期に入り、大人に近い食事へと進んでいきます。母乳やミルク中心の頃に比べると、自然に水分や食物繊維の摂取量が減りやすく、それが便秘の原因となります。
白ごはんやパン、肉や魚に偏ると腸を動かす力が弱まり、便が硬くなりやすいのです。特に野菜や果物、豆類、海藻類を十分に摂れていない場合、便秘が悪化しやすくなります。
食生活の偏りをなくし、主食・主菜・副菜を意識して組み合わせることが便秘予防につながります。
水分不足・運動不足
1歳になると授乳回数が減り、食事中心の生活になるため、以前より水分が不足しやすくなります。子どもは自分で「のどが渇いた」と訴えにくいため、保護者が意識的に水分を勧める必要があります。
麦茶や水を少量ずつこまめに与える、食事の前後に汁物や果物を取り入れるなど、自然に水分を補える工夫が大切です。ただし、砂糖入り飲料やジュースはむし歯や食欲低下の原因になるため常用は避けましょう。
また、室内遊びが多く運動不足になると、腸のぜん動運動が弱まり便秘につながります。体を動かすこと自体が腸の動きを助けるので、散歩や外遊びを日常に取り入れましょう。
生活リズムの乱れ・心理的要因
昼寝や就寝の時間が不規則になると生活リズムが乱れ、便意が起こりにくくなります。朝はしっかり起きて朝食をとる、昼寝や就寝時間を一定に保つなど、リズムを整えるだけでも便秘改善に役立ちます。
また、1歳はトイレトレーニングの準備期に入る子もいますが、排便を急かされたり失敗を叱られると「出すのは怖い」という気持ちにつながります。
さらに、保育園の入園や引っ越しなど環境の変化によっても便秘になることがあります。心理的な負担を与えず、排便の成功体験を積み重ねることが大切です。
家庭でできる便秘対策

原因を理解したうえで、家庭でできる工夫を取り入れていくことが大切です。水分、食物繊維、乳酸菌、運動やマッサージなど、日常に無理なく取り入れられる方法を紹介します。
こまめな水分補給
1歳児はまだ「のどが渇いた」と自分で伝えるのが難しく、遊びや食事に夢中で水分補給を忘れてしまいます。便秘予防の基本は「少しずつこまめに与えること」です。
起床後、食事やおやつの前後、外遊びやお風呂の後など、生活の節目で一口でも差し出しましょう。水や麦茶を基本とし、スープや果物からの水分も補給源に含めると安心です。
特に便秘がちのときは、食事の最初に汁物を出すと腸の動きがスムーズになります。ストローやコップの練習を兼ねて「自分で飲めた」体験を積ませると、飲水習慣も身につきます。
食物繊維を含む食材を取り入れる
便を柔らかくする水溶性食物繊維(オートミール、りんご、バナナ、海藻など)と、便のかさを増す不溶性食物繊維(さつまいも、かぼちゃ、にんじん、きのこなど)をバランスよく摂ることが大切です。
1歳児の場合は、やわらかく煮て小さく切るなど、噛みやすく飲み込みやすい形状に調理する工夫が必要です。
例えば朝は「オートミール+ヨーグルト+果物」、昼は「野菜入りやわらかうどん」、夜は「さつまいもとブロッコリー入りのスープ」といった形で、1日の中に自然に取り入れると続けやすいです。
便秘予防に役立つ食材例
| 食材 | 特徴 | 調理例 |
|---|---|---|
| さつまいも | 不溶性繊維で便のかさを増やす | 蒸して一口大に、おやつに |
| バナナ | 水溶性繊維で便をやわらかく | ヨーグルトに混ぜて朝食に |
| オートミール | 食物繊維+鉄分豊富 | おかゆ風、パンケーキ風に |
| 納豆 | 乳酸菌で腸内環境を整える | ごはんにかけて夕食に |
| りんご | ペクチンで便を柔らかく | すりおろしやコンポートに |
乳酸菌やオリゴ糖の活用
ヨーグルトや納豆、みそなどの発酵食品は腸内環境を整える働きがあります。オリゴ糖は腸内の善玉菌のエサになり、便秘改善をサポートします。
おすすめは「プレーンヨーグルト+刻んだ果物+少量のオリゴ糖」。甘みが自然で、子どもも食べやすいです。
乳酸菌やオリゴ糖は即効性があるわけではないので、2〜3週間続けて腸の変化を観察しましょう。子どもによって合う食材は異なるため、1つの方法で変化がなければ別の食品を試してもよいでしょう。
お腹のマッサージや適度な運動
お腹を「の」の字に沿って時計回りにやさしくさするマッサージは、腸のぜん動を促します。おむつ替えや入浴後など、子どもがリラックスしているときに取り入れると効果的です。
また、1歳児は歩き始める時期なので、手をつないで短時間歩く、公園で砂場遊びをする、室内ではボールを転がして追いかけるなど、無理なく体を動かす遊びを日常に取り入れると良い刺激になります。運動の後は必ず水分補給を忘れないようにしましょう。
便秘予防に役立つ食事例と生活習慣

一度便秘を解消しても、再発を防ぐには予防が重要です。食事の工夫や生活リズムの整え方を具体的に紹介し、毎日の習慣として取り入れられるヒントをまとめます。
おすすめの食材とレシピ例(野菜・果物・発酵食品)
便秘予防のためには「腸を動かす食材」を毎日どれか1つ取り入れる意識が有効です。
朝食は「ヨーグルト+バナナ+オートミール」でスタート、昼食は「豆腐とわかめのやわらかうどん」や「かぼちゃとにんじんのポタージュ」、夕食は「納豆ごはん+野菜スープ」でバランスを整えましょう。
おやつには「蒸したさつまいも」や「りんごのすりおろし・コンポート」など、1歳児でも食べやすい柔らかい調理法が安心です。
便秘になりやすい食品
牛乳は栄養価が高いですが、1日に200ml前後が目安です。飲みすぎると食事が入らなくなり、食物繊維や鉄分が不足して便秘や鉄欠乏を招きやすくなります。
白ごはんやパンなど精製された炭水化物ばかりに偏るのも要注意です。また、スナック菓子や甘いジュースは腸内環境を乱しやすいため、日常的に与えるのは控えましょう。
規則正しい生活リズムづくり
腸の働きは生活リズムに大きく影響されます。特に「朝起きる→朝食を食べる→排便を促す」という流れを作ると便通が整いやすくなります。朝食後におむつ替えやトイレに座らせる習慣をつけると、排便のリズムが身につきやすいです。
また、昼寝や就寝時間を一定に保ち、日中しっかり体を動かすことも重要です。お腹のマッサージを朝食後や寝る前に取り入れると、排便のきっかけ作りにもなります。
受診が必要な便秘のサイン

多くの便秘は家庭での工夫で改善しますが、なかには医療機関の受診が必要なケースもあります。ここでは特に注意すべきサインを具体的に整理します。
強い腹痛や嘔吐を伴う場合
お腹が痛くて激しく泣き続ける、嘔吐を繰り返す、便やおならがまったく出ないなどの症状は、緊急性のある病気の可能性があります。すぐに小児科を受診しましょう。
便に血が混じる場合
硬い便による肛門の傷であれば一時的な場合も多いですが、繰り返したり血の量が多い場合は注意が必要です。黒っぽい便やタール状の便が出るときは、消化管からの出血の可能性があるため早急に受診しましょう。
排便困難が続く場合
数週間以上便秘が続く、排便を強く嫌がる、食欲不振や体重増加が見られない場合は、慢性便秘の可能性があります。早期に対応し「痛くない排便経験」を作ってあげることが大切です。
1歳児の便秘に関するよくある質問
最後に、保護者から寄せられることの多い疑問をQ&A形式で整理しました。牛乳や果汁、浣腸の使い方など、気になるトピックを確認しておきましょう。
Q1:牛乳は便秘を悪化させますか?
A:牛乳は1日200ml前後が目安です。飲みすぎると食事量が減り、鉄分不足や便秘につながることがあります。
Q2:果汁は便秘対策に効果がありますか?
A:りんごやみかんなどの果汁は便をやわらかくする効果が期待できますが、糖分が多いため常用は避けましょう。果物そのものを柔らかく調理して与える方が望ましいです。
Q3:浣腸は家庭でしてもいいですか?
A:一時的に便を出すには有効ですが、繰り返すと自力で排便する力が弱くなることがあります。家庭で頻繁に使用せず、必要な場合は必ず医師の指導に従いましょう。
Q4:便秘のときに避けた方がいいおやつは?
A:ポテトチップスやチョコレートなど脂肪分・糖分の多いお菓子は腸内環境を乱しやすいため控えましょう。代わりに「蒸しさつまいも」や「フルーツヨーグルト」など腸にやさしいおやつを取り入れてください。
(まとめ)1歳児の便秘対策|原因・家庭でできる解消法・受診の目安
1歳児は食生活や生活リズムの変化から便秘になりやすいため、水分・食物繊維の摂取、規則正しい生活を心がけましょう
1歳児の便秘は、食事の偏りや水分不足、生活リズムの乱れ、心理的な要因が重なって起こることが多いです。
対策の基本は「水分をこまめに与える」「やわらかく調理した野菜や果物で食物繊維を摂る」「規則正しい生活リズムを心がける」ことです。お腹のマッサージや適度な運動も効果的です。
多くは家庭での工夫で改善できますが、強い腹痛や嘔吐、血便、体重増加の停滞が見られる場合は、早めに医療機関へ相談しましょう。小さな工夫と早期の対応が、お子さんの快適な毎日と健やかな成長を支えます。
<出典>
- 厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」
- 神戸大学医学部附属病院小児外科「便秘症」
- 日本小児栄養消化器肝臓学会「こどもの便秘」
- 長野県医師会「「乳糖不耐症」と「牛乳アレルギー」」
- 伊勢原市「乳児さんのこんなときは・・・便秘・下痢編」



