サウナで汗をかくことで、汗と一緒に疲労物質が排出されます
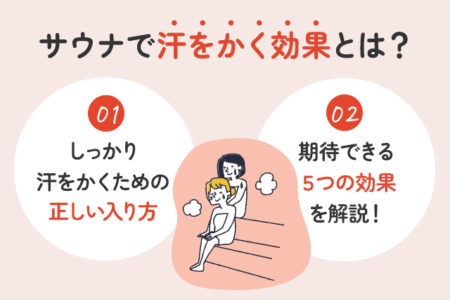
サウナで汗をかくと、どんな効果が得られるのでしょう。熱い室内で大量の汗をかくサウナには、主にリフレッシュ効果や健康・美容に良い効果が期待できるとされています。
近年サウナ―と呼ばれるファンも増加している人気のサウナですが、サウナで汗をかくことが実際にはどのような効果につながっているのか、サウナの効果を引き出すにはどんな入り方がいいのかなど、今注目の気になるサウナについて紹介します。サウナに入る際にはどんなことに気を付けなければならないのかも紹介しているので、参考にしてみてください。
目次
サウナで整うとは「頭がスッキリした爽快感」
サウナとは
一般的なサウナとは、フィンランド式のドライサウナを指します。室内を遠赤外や蒸気などで80~100℃の高温に保ち、その周りに設置してある木製の椅子に座ってじっくりと汗を流します。サウナ→水風呂→外気浴・休憩がワンセットとされ、これを数回繰り返していきます。
サウナで「ととのう」とは
サウナでは、アツアツになった身体を水風呂で一気に冷ますことを繰り返します。その後の休憩の際に得られる「爽快感」や「多幸感」、頭が冴えてすっきりした感じのことを、「ととのう」と表現しているのです。
サウナで身体を温めることで、血流が一気に良くなり一種の興奮状態になります。そのままの状態で水風呂に入ると、身体が冷えて興奮が抑えられます。頭は興奮した状態、ただし体は落ち着いている状態、この状態がいわゆる「ととのう」です。
心身のリラックス効果で「ととのう」
サウナと水風呂を交互に利用することで、極端な体温の上昇を避けて、少しずつ身体の中から温める効果があるため、身体がほっとするリラックス効果も得られます。このリラックス効果も「ととのう」状態のひとつです。
サウナでは汗と一緒に「疲労物質を排出」している
サウナで「ととのう」ことで感じられる効果はいくつかありますが、具体的に5つに分けて説明します。
リラックス効果
緊張やストレスを感じると、身体がこわばり、そのこわばりで筋肉が血管を圧迫します。その結果、血流が悪くなることで血圧が高くなり、ドキドキと感じるのが動悸の原因です。
サウナで温まることで、筋肉のこわばりが解け、リラックスした状態となるのです。
またサウナの中では、スマートフォンやPCを見ることができません。そのため瞑想をしたり、自分の内側に向けゆっくりと深い呼吸することが多くなります。体の底から心を落ち着かせることができるため、普段時間に追われているビジネスマンや、常に何かが気になってしまう人など、何もない空間であえて何も考えない。そんなほっと一息つける空間はストレス解消や心の疲労回復にも期待できです。
疲労回復効果
心と体がリラックスできるサウナは、疲労回復にも大きな効果が期待できます。特にスポーツの後や日々の仕事の肉体疲労にオススメです。
肉体的な疲労回復には、汗をかきやすくする「刺激浴」を、ストレスや不安などの心のリラックスを重視するのであれば、「ぬるめのサウナ浴」を選ぶようにしましょう。
刺激浴はたっぷりと汗をかくことで疲労回復に、ぬるめのサウナ浴はじんわりと汗をかきながら、ゆっくりと心を落ち着かせることでストレス解消につながります。
快眠
サウナに入ると、運動したような一定量の汗をかきます。さらに興奮状態となるため、適度な疲労を感じるのです。この適度な疲労感により、快眠効果が高いとされています。
またサウナでは血行が良くなるので、身体が内側からあたたまり、睡眠の質を高めてくれるでしょう。
肌荒れ改善
サウナで汗をかくことで、汗と一緒に皮膚から余分な脂や汚れ・老廃物が排出されます。毛穴がすっきりすることで、結果的にニキビができにくくなる、ニキビ予防にも効果的だと言われています。
また、サウナには体臭改善にも効果があると言われています。汗腺の働きが鈍くなると体臭が強くなってしまうことがあるため、サウナで汗腺の働きを促し、老廃物を排出させることで体臭の改善にも期待できます。
ただし、汗を放置しておくと肌荒れや体臭を悪化させる原因となってしまうため、汗をしっかリ流すことも重要なポイントです。
血行促進
サウナはお風呂と違い、水圧もかからず体が温まり、血管が広がることで通常時の約2倍と言われるほど大量の血液が体を流れます。
血流が良くなることで代謝が高まり、必要な酸素や栄養を細胞に届けてくれます。血行不良は、肩こりや腰痛・冷え性の原因とも言われていますので、多くの不調の改善にもおすすめです。
しっかり汗をかくための「正しい入り方」

Ice Baths Australia(https://theicebath.com.au/)
それではサウナに入る正しいマナーや、基本的な入り方について見ていきましょう。
1.まずは水分補給
サウナでは300ミリリットルほどの大量の汗をかきます。脱水症状をおこさないために、入る前にたっぷりと水分補給をしておきましょう。
2.身体を洗う
サウナに入る前には、髪や身体をよく洗いましょう。いろいろな方が利用するサウナや戦闘では、最初に身体を清潔にしておくのがエチケットです。
また皮膚や汗腺に汚れがついたままだと、汗をかきにくくサウナの効果が下がってしまいます。さらに蒸気のこもった室内では、臭いが出てきやすくなりますので、あらかじめ汚れをしっかり落としておきましょう。
水滴を垂らしながらサウナ室に入ることはマナー違反ですので、タオルできちんと水気を拭き取ってから入りましょう。
3.サウナ室へ
頭と身体を洗ったら、サウナ室へ入ります。サウナの種類や温度・湿度にもよりますが、初めてサウナに入ったときや、通い始めの頃は10分を目安にしましょう。決して無理をせず、最初は5分前後から、自分の身体と相談しながら決めてください。
サウナの多くは室内が二段になっており、上段の方が下段よりも熱くなっています。初心者の方や熱いと感じたら無理をせず、下段からスタートして、ゆっくり汗をかきましょう。
4.水風呂に入る
サウナ室から出てきたら、まずは汗をかけ湯で流します。そのあと水風呂へ入りましょう。目安時間は2分ですが、水風呂に慣れていない時は、腕や足など身体の一部にお水をかけることからはじめてみてください。徐々に冷水をかける箇所を増やし、慣れてきたと感じたら肩まで入ってみましょう。
5.サウナ→水風呂を繰り返す
サウナで汗をかき、水風呂へ入るというこの流れを2回~3回ほど繰り返します。サウナと水風呂を繰り返すことで、「ととのう」というリラックス状態に入りやすくなります。
6.休憩
サウナと水風呂を繰り返したら、一度休憩をしましょう。約10分間が目安です。休憩用のイスが用意してありますので、ゆっくりと呼吸をしてリラックスしましょう。じわじわ体が温まり、自分の心や身体に集中することで頭がすっきりとした感覚を得られるでしょう。
水分補給が重要!サウナに入る際の「注意点」
最後に、サウナに入る際の注意点を紹介します。
水分補給が重要
大量に汗をかくサウナでは、入浴後はもちろん入浴前や休憩中にも、しっかりと水分補給を意識しましょう。水分補給をすることで発汗作用が促進し、老廃物の排出を高めることができます。
ただし、サウナ中の水分補給はおすすめできません。水分がすぐに血液に溶け込み、老廃物の排出効果が弱くなってしまいます。
休憩がポイント
「ととのう」整う状態は、休憩をした瞬間に訪れます。サウナと水風呂で終わらせることなく、ちゃんと休憩時間を確保しましょう。休憩中にじわじわと温まることで、血流が促進され、脳まで酸素が行き渡り深いリラックス状態を味わえます。
入浴時間にも注意が必要です。適度に汗をかけばそれでOK。熱いのをがまんするのは、かえって体に負担をかけてしまいます。最後はシャワーで汗を流し、水風呂に30秒~1分程度入ります。
ただし、いきなり入るのは危険。水を手足から徐々にかけて慣らしてから入りましょう。もちろん心臓が弱いなど健康に問題のある場合には、サウナを利用してはいけません。
身体を拭いてから入るのがコツ
身体に水分が残ったままでサウナに入ると、その水分が一気に高温になり身体の表面温度が上がります。そのため、すぐに息苦しさを感じ、サウナに入っていることができなくなってしまいます。
サウナでは内側から温めることがポイントなので、身体の表面が先にあたたまってしまうことは避けましょう。水分をきちんと拭き取っておくと、汗がかきやすくなり効率よく身体を温めることができることができます。
それでも無理はNGです。お酒を飲んだ後のサウナや体調が優れない時のサウナは危険なでやめましょう。また食事の食後もおすすめできません。体調を万全にして、サウナを楽しんでください。
(まとめ)サウナで汗かく効果とは?ちゃんと整う入り方のコツ
サウナで汗をかくことで、汗と一緒に疲労物質が排出されます
サウナで汗をかくと、「整う」ことによるリフレッシュ感をはじめ、疲労回復や美肌効果、ストレス解消、快眠効果など身体にさまざまなメリットが生じます。熱いサウナに入り身体を温めてから水風呂で身体の熱を冷まし休憩を取るといった正しいサウナの入り方をすると、現在人気を集めている整う効果によりサウナならではの体調改善が期待できるでしょう。
サウナに入る際には、注意点があります。体調不良時やアルコールを飲んだ後などに無理して入ると、危険な場合もあります。
正しい入り方でサウナを利用することで、より効果的に健康・美容に役立てられるでしょう。
<参考文献>
- 総合東京病院「サウナは本当に健康にいいのか?」
- 日本サウナ・スパ協会「サウナならではの身体効果」
- 日本スポーツ協会「サウナ入浴の生理学的研究」



